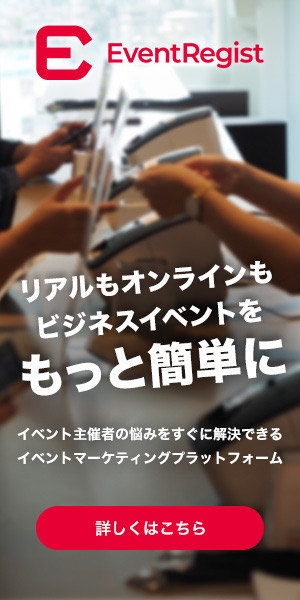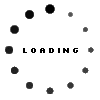- Home
- Interview, ニュース, 特集個別ページ
- 空間デザインはIllusionaire だ 〜SLUSH TOKYO
空間デザインはIllusionaire だ 〜SLUSH TOKYO
- 2019/2/28
- Interview, ニュース, 特集個別ページ
- SLUSH, SLUSH TOKYO 2019, SLUSH ライブみたい, slushtokyo, SLUSH 演出, スタートアップイベント, 東京ビッグサイト, 田村一馬, 空間デザイン

– 特集 クライアントと創る空間デザイン –
カンファレンス
今回のクライアントは…. SLUSH TOKYO
–SUN EFFECTS OY
SLUSH TOKYO 田村一真さん
右: SUN EFFECTS OY のMatti Jykyläさん
――SLUSH TOKYOのデザインはどのようにつくられているのですか
マッティ 私はイベント全体のデザインを担当しています。フロアプランからステージの造作、2D・3Dデザイン、照明、映像まで携わっています。しかし、全体のデザインというのは、イベントのアイデンティティをつくることだと考えています。
――イベントのアイデンティティをつくるというのはどういうことなのですか?
マッティ イベントには開催する目的やコンセプトがありますよね。それを言葉で説明するのではなく、そこに来れば自然に感覚的に理解できるように具現化することです。
田村 ステージの周りを囲むように360度参加者の席を配置したデザインも、SLUSHという場をこういう風にしたいという僕らの想いを実現してくれました。打合わせの途中からすぐスケッチを書きはじめて…
マッティ アイデア出しの段階は手書きがいいですね。デバイスを使うより早いし、書いては見せ、話し合ったアイデアをどんどん盛り込んでいきます。
――デザインにかかる時間は?
 マッティ 今回は7か月くらいですね。その間に細かい修正は毎日のように、一から作り直しも4回ありました。私は気が変わりやすいんですよ。でもイベントのデザインは変更を重ねてよくなるのです。プロジェクトを進める間にイベントの内容が見えてきたり、新しいアイデアが出るたびに変えていきます。
マッティ 今回は7か月くらいですね。その間に細かい修正は毎日のように、一から作り直しも4回ありました。私は気が変わりやすいんですよ。でもイベントのデザインは変更を重ねてよくなるのです。プロジェクトを進める間にイベントの内容が見えてきたり、新しいアイデアが出るたびに変えていきます。
――周りの人は大変ですね
田村 僕らも協力会社の人も、イベントを良くするための変更だと理解しているので「OK、やろう」ってなりますよ。
マッティ 私はイベントに関わって30年、完璧なイベントを作れたことはないし、見たこともない。だから常に新しいことに挑戦します。SLUSHはその点がとくに重要です。新しい社会をつくるスタートアップのイベントが、「安全だから、昨年と同じようにやろう」では絶対ダメですよね。
――SLUSHの会場はイノベーティブでかっこいいのですが、そのポイントは?
マッティ 会場の照明を落として暗闇をつくることですね。そのなかでコンテンツを配置していき、照明や映像、レーザーなどで演出することで、全体をいちように見せるのではなく、どこにフォーカスしてもらうか、という設計ができるようになります。イリュージョンのようになにもないところから、突然なにか現れるような感じです。私たちはフェイクではなく現実のものを、参加者の目の前にドラマティックに登場させるのです。
――雰囲気やコンセプトといった目に見えないことの具現化は大変だと思うのですが。
マッティ たしかにむずかしいですよね。でも、それが私の仕事なんです。