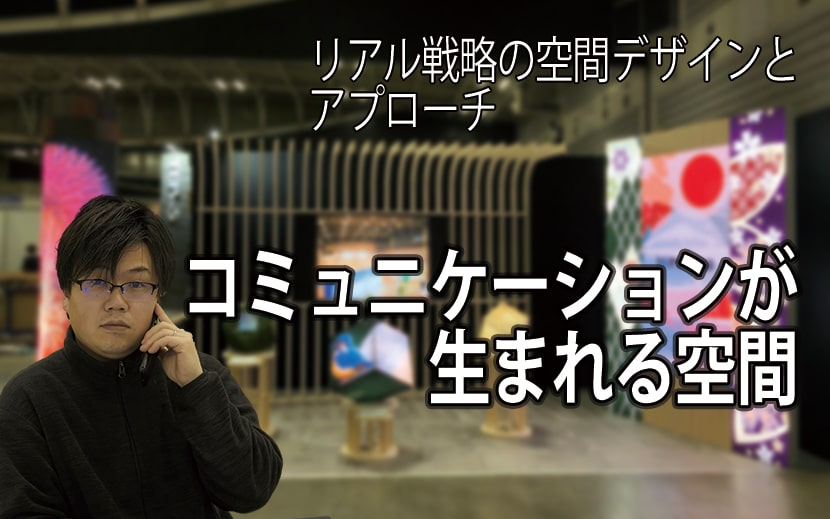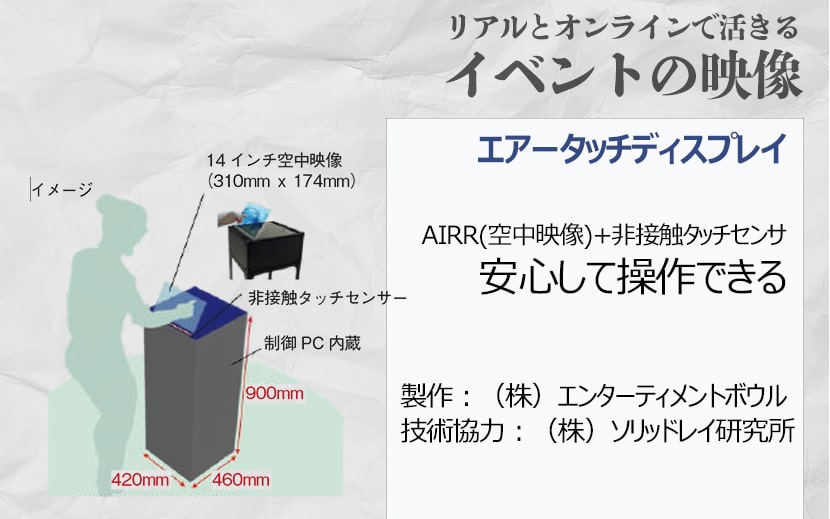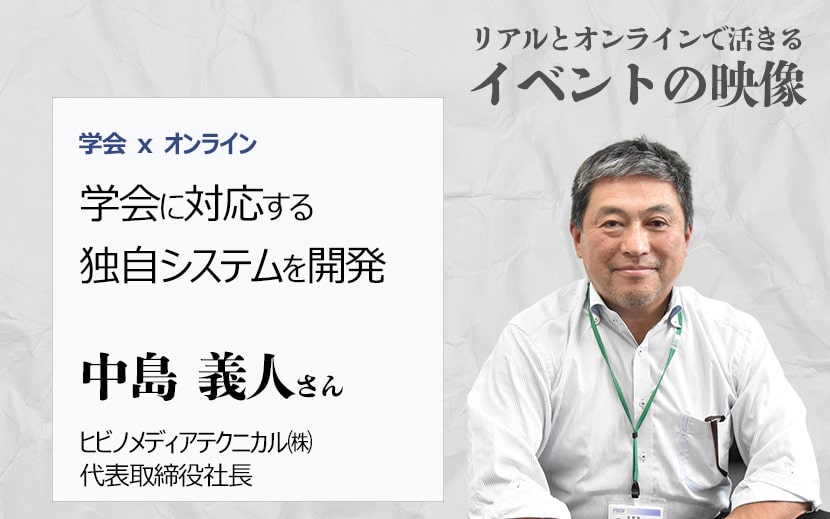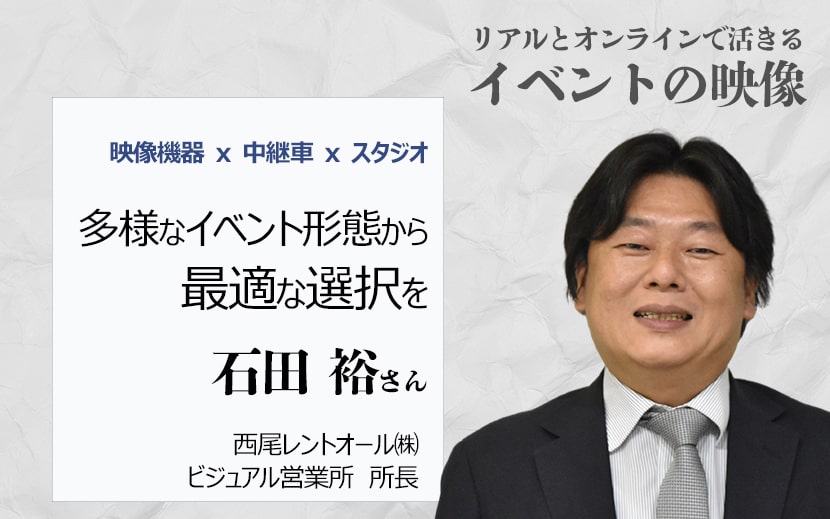カテゴリー:特集個別ページ
-
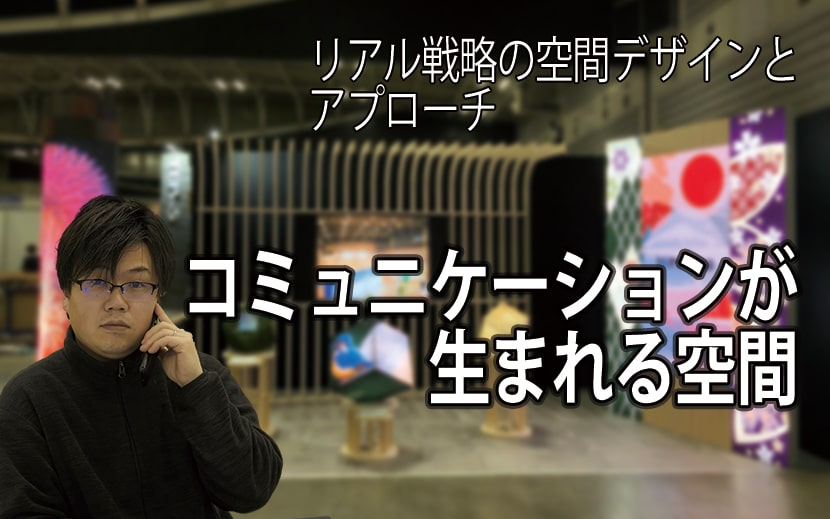
特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ
コミュニケーションが 生まれる空間
池田 和宏さん 東京企画装飾株式会社 TEProS デジタルプロモーショングループ
展示会ブース 東京企画装飾(自社ブース)
S…
-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ
多くの人に 体験してもらう
駒井 明日香さん サクラインターナショナル株式会社
展示会ブース ソフトバンク株式会社
SEMICON JAPAN 2021
解決した…
-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ
空間に時間の概念をプラス
長崎 英樹さん シンユニティグループ 株式会社タケナカ 専務取締役
地域プロモーション - 神戸ウォーターフロント アートプロジェクト
1…
-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ
共創型展示会×大型展示会=成果++
竹村 尚久さん SUPER PENGUIN 株式会社 代表取締役
未来のイベントの在り方を様々な視点から模索し、トライしていく有志…
-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ
リアル戦略の空間デザインとアプローチ
「顧客創造」するマーケティングの場は、DXの浸透で届く範囲も、手法も選択肢が増え、細分化・多様化している。オンラインでもできるよう…
-

特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像
テレプレゼンスロボット×展示会/国際会議 遠隔地から見せる、参加できる
temi
映像センター イベント映像事業部が今年新たに導入したのは、遠隔地からの映像を届…
-
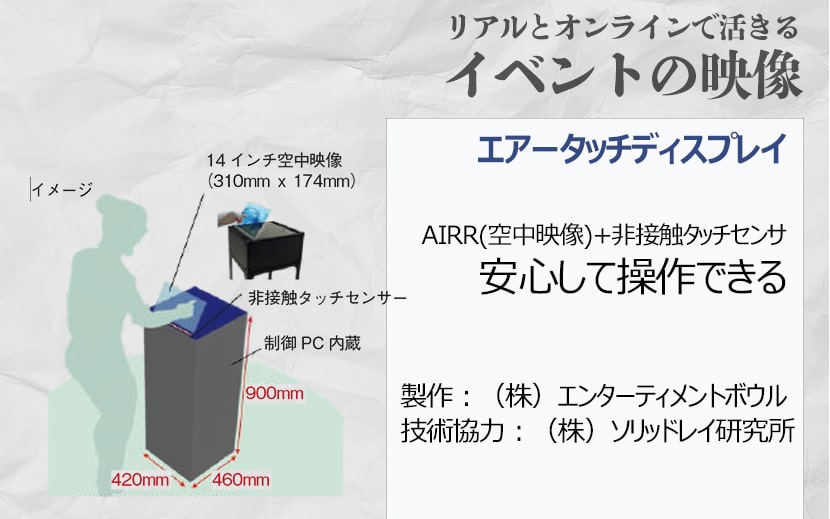
特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像
AIRR(空中映像)+非接触タッチセンサ 安心して操作ができる
エアータッチディスプレイ
「エアータッチディスプレイ」(製作:(株)エンターテイメントボウル、…
-

特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像
映像機器 小型軽量化で使い勝手良いRGBプロジェクター
ウシオライティング(株) クリスティ営業部 代表取締役社長 根岸 健次郎さん
ドバイ万博の公式プロジェク…
-
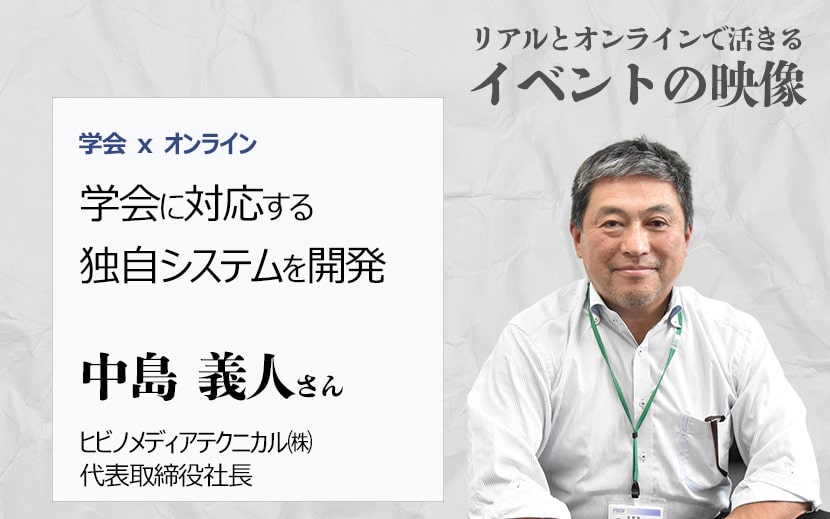
特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像
学会 x オンライン 学会に対応する独自システムを開発
ヒビノメディアテクニカル(株) 代表取締役社長 中島 義人さん
学会や国際会議、展示会の映像機器のレンタ…
-
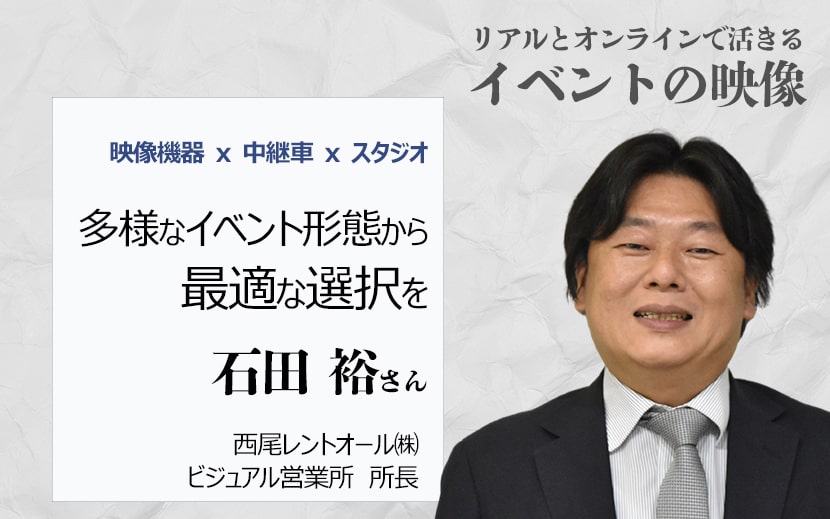
特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像
映像機器 x 中継車 x スタジオ 多様なイベント形態から最適な選択を
西尾レントオール(株)レントオール事業部 ビジュアル営業所 所長 石田 裕さん
イベント…
PAGE NAVI
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 18
- »